【 連携事例紹介 】// Contents

企業版ふるさと納税の活用メリットを最大化するためには、適切な視点で寄付先を選ぶことが大切です。また、自社に合う寄付先が思いつかない場合、各自治体や国のホームページで公開されている成功例を参考にするのも一つでしょう。
この記事では、企業版ふるさと納税の寄付先選びにおけるチェックポイントと、全国の自治体が用意する地方創生プロジェクトの事例を紹介します。事例のなかでは、企業がそのプロジェクトを寄付先として選んだ理由も解説します。自社にとってメリットの大きい寄付先を選びたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
寄付先選びのチェックポイント
企業版ふるさと納税を活用して多くの効果・メリットを得るためには、自社に合う寄付先を選ぶことが大切です。ここではまず、寄付先が自社とマッチするかどうかを見極めるためのチェックポイントを4つ紹介します。
①自社の寄付方針との一致

最も効果的な寄付先の選び方は、最初に自社の寄付方針を決めたうえで、その内容に合う寄付先を探していくことです。寄付の方針は、自社のCSR・サステナビリティ活動の方針や事業・経営方針と関連付けられている必要があります。
CSRは「Corporate Social Responsibility」の略語であり、日本語では「企業の社会的責任」と訳される概念です。CSRは、企業が社会・環境などと共存しながら持続的な成長を図るために責任ある行動をとり、説明責任を果たしていくことを求める考え方になります。
たとえば、自社サイトのCSRページで「人権尊重」を掲げていると仮定します。この場合、「人権尊重」に関連する寄付方針を考えたうえで、その目的に合致する地方創生プロジェクト(寄付先)を選ぶイメージでしょう。
寄付方針を軸に選定を行うと、寄付先と自社のCSR方針との整合性がとれることになります。結果として、企業ブランドやステークホルダーからの評価を高めやすくなるでしょう。
②自社の戦略や事業とのシナジー
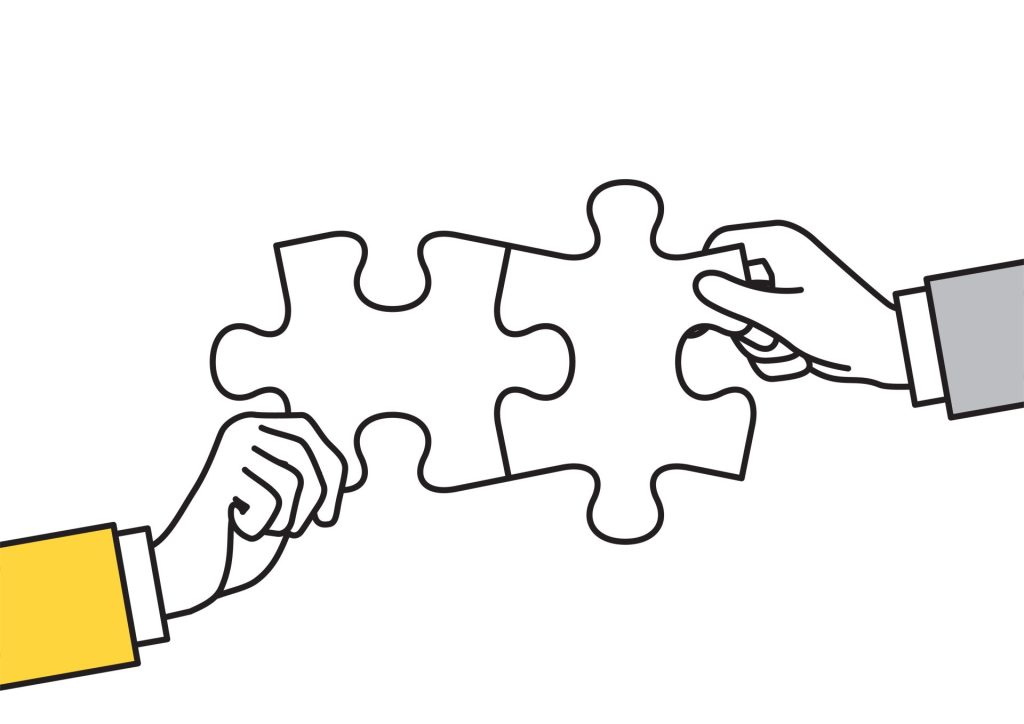
寄付金以外の関わり方を重視する場合、自社製品・サービスと関連性が高い事業テーマを選ぶのも一つです。
たとえば、近年の日本では、企業版ふるさと納税などの仕組みを活用していわゆる「災害の備え」に力を入れる自治体が多くなっています。そこで自社が保存食や発電機などを取り扱っている場合、災害用備品の配備強化を行う自治体に寄付をするのも有効です。
災害関連で自治体とのパートナーシップを構築すれば、定期的な商品提供を通じた中長期の関わりが生まれたりもします。
また、「創業者の出生地」や「(自社製品の)原材料の一大産地」といったポイントから自社と縁のある自治体を選定すると、寄付先への愛着や関係性などをアピールしやすくなるでしょう。
③付随して得られる恩恵は魅力的か

寄付先を選ぶ際には、経済的な利益に当たらない見返りの内容にも注目しておきたいところです。
たとえば、自治体が運営する公式SNSでの紹介、報道機関へのプレスリリースといった広報・PR面のベネフィットは、寄付およびCSRの取り組みを幅広いステークホルダーにアピールするうえで有効となります。
また、地方創生プロジェクトの視察や社員ボランティアの受け入れ機会があると、若手人材の育成やクロス部門連携の場としても活用できるといったメリットもあります。
➤企業版ふるさと納税のメリット・デメリットを徹底比較!向いている企業とは?
④事業の質は担保されているか

自社のESG評価を高めるうえでは、寄付事業における社会的な価値の大きさも重視したいところです。ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字をとって作られた言葉で、主に投資判断に使われる基準です。ESG評価は、社会・環境および経済のすべてにメリットをもたらすビジネス設計になっているかどうかを評価する考え方になります。
ESGとCSRの両面からステークホルダーにアピールするのであれば、寄付対象プロジェクトのガバナンスや事業体制にも注目したほうがよいでしょう。また、社会投資に関する透明性の高い情報開示をしていくうえでは、事業の実施自治体から届く「事業実施報告書」などを中心とするアウトプットの品質も重視する必要があります。
企業版ふるさと納税の事例
はじめて企業版ふるさと納税を活用する場合、各自治体のホームページで公開されている「地方創生プロジェクトの計画」や「寄付企業の情報」を寄付先選びの参考にするのも一つです。内閣府でも、企業版ふるさと納税の「活用事例集」を公開しています。
自治体のなかには、企業が「そのプロジェクトを選んだ理由」や「地方創生への想い」などまで詳しく紹介しているところもあります。こうしたページを参考にすると、各社の寄付方針や動機などもイメージしやすくなるでしょう。
ここでは、5つの自治体における地方創生プロジェクトの概要(計画)と、企業がその寄付先を選んだ理由を紹介します。
町に回帰する人材育成サイクルを構築(北海道東川町)
北海道東川町では、子どもたちの郷土愛を育み、将来的に「人財」として町に戻ってくるサイクルを構築するためのプロジェクトを計画しました。具体的には、起業支援や国際教育の推進、奨学助成などを行います。町独自の「オフィシャルパートナー制度」を構築しているところも、大きな特徴になります。
北海道東川町は、「人材育成」ならびに「オフィシャルパートナー制度」の2点で企業から注目されることが多いです。
人材育成のプロジェクトであれば、たとえば自社の育成ノウハウやキャリア支援の仕組みを活用して、地域の人々に貢献することも可能となります。また、町独自のパートナー制度は、地方自治体との関わりを一度きりの寄付で終わらせたくない企業にとって、魅力的な仕組みになるでしょう。
参照:内閣府地方創生推進事務局|企業版ふるさと 納税活用事例集
鴻ノ池周辺のまちづくり|旧奈良監獄との連携プロジェクト(奈良県奈良市)
奈良県奈良市が実施したのは、運動公園と旧奈良監獄という2つの大きな施設および周辺エリアの特性を活かし、「世界遺産のある奈良」に新しい魅力を創出するプロジェクトです。
運動公園エリアの整備では、ランニングステーション&コースの整備やスケートボードパークの新設などを通して、幅広い市民が利用できる憩いの場を生み出します。また、運動公園に隣接する重要文化財・旧奈良監獄は、ホテルに改修することで、多くの市民や観光客が楽しめる施設に発展させる方針です。
このプロジェクトは、大手リゾート会社や不動産関連サービス会社など、さまざまな業種からの寄付を受けています。
リゾート会社では、明治時代の素晴らしい建物の活用が、観光業の将来における「要」になるという認識から、寄付および連携を決めています。不動産関連サービス会社では、各施設の特性を活かす取り組みのなかで自治体およびさまざまな企業が連携し、幅広い人々を惹きつけるビジョンに共感して、寄付を行っているようです。
参照:奈良市|特集:企業版ふるさと納税でつながる「企業とまちの新しい関わり方」
令和6年能登半島地震|被災者支援、復旧・復興(石川県ならびに各市町村)
石川県ならびに県内の各市町村では、令和6年1月に発生した能登半島地震の被災者支援や復旧・復興を目的とした企業版ふるさと納税を受け付けています。
能登半島地震のように広範囲の自然災害では、寄付先の選び方も非常に多彩です。たとえば、北陸エリアの不動産総合サービス企業では、珠洲市や輪島市といった被害が特に大きい7つの自治体に対して各100万円ずつ、合計700万円の寄付を行っています。
また、能登半島地震の場合、市区町村ではなく石川県にまとめて寄付をすることもできる形です。
こうした被災地支援系のプロジェクトは、「今後も被災地に寄り添い続けたい」や「企業として、持続的かつ実効性の高い支援を届けたい」という想いから選定されることが多いです。また、寄付金とあわせて、社員による現地ボランティアや定期的な物資支援などを行うケースもあります。
参照:PR TIMES|さくらホームグループが「企業版ふるさと納税」で能登半島地震の復興支援を実施
「ひと」・「まち」・「暮らし」今日を支え、未来を創るまちづくり(長崎県島原市)
長崎県島原市のプロジェクトは、自然・歴史・安全安心・人材・活力といったさまざまな観点から、未来を創る「まちづくり」をするというものです。人口減少や少子高齢化が進む地域の課題に対応するため、子育て支援や移住促進、雇用創出など、地域の活性化につながる幅広い取り組みが対象となります。
このプロジェクトを選んだ企業のなかには、自社のコーポレートメッセージおよびビジョン、ミッションとの深いシンクロを選定理由として挙げるところもあります。たとえば、「まちづくり」や「ふるさとの魅力や潜在資源の創出」、「次世代への継承」といったキーワードから、寄付先とつながるイメージです。
参照:島原市|企業版ふるさと納税 ~島原市にエールを!~
スケートボードの聖地「むらかみ」セカンドプロジェクト(新潟県村上市)
新潟県村上市が計画したのは、以前から存在していた民間スケートボード施設を活用し、交流人口の拡大や周辺地域の活性化につなげるプロジェクトです。
東京オリンピックでスケートボード競技が正式種目になったことや、その施設で練習をしていた選手が五輪でメダルを獲得するといった機運を活かした事業でもあります。
このプロジェクトの大きな特徴は、自治体および地域住民よりも、スケートボード施設を利用する「ジュニア選手などの子ども・若者」への応援を目的とする企業が多い点です。
村上市自体への関心や地域復興を願う企業ももちろん多くありますが、「国内外のスケートボード競技者・愛好者」への支援を寄付の理由とする会社が多い点は、一般プロジェクトにはあまり見られない特色でしょう。
参照:村上市|スケートボードの聖地「むらかみ」セカンドプロジェクト【2020年度から2024年度】
企業版ふるさと納税制度の活用方法
企業版ふるさと納税の制度は、ここまで紹介した各自治体のほかに、NPOなどの非営利団体への寄付でも活用することが可能です。ここでは、県や市町村以外が主体となるプロジェクトで企業版ふるさと納税の仕組みを使う場合のポイントと、この制度を活用できるNPO事業の具体例を紹介しましょう。
NPOなど非営利団体への寄付にも利用可能
NPO・NGO・CSOなどの団体が実施する取り組みのうち、地域の課題解決に貢献するものを自治体が地方創生事業として認定し、企業版ふるさと納税を活用して寄付を募る仕組みがあります。NPOなどへの寄付を検討している場合も、この制度を利用することで、普通の方法で寄付するよりも少ない自己負担額で寄付できる可能性があります。
企業版ふるさと納税を活用して寄付額から「損金算入の約3割」+「税額控除の最大6割」が差し引かれた場合、寄付企業の実質的な負担額は約1割まで圧縮されることになるでしょう。
少ない自己負担額で非営利団体への寄付を行いたい場合、各団体に問い合わせを行い「企業版ふるさと納税に対応しているかどうか?」を一度確認してみてもよいかもしれません。
企業版ふるさと納税で支援できるNPO事業の例
広島県神石高原町に本部をおく認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパンは、1996年設立の日本発のNGOです。国際人道支援、災害緊急支援、保護犬事業を中心に、助けを必要とする命を救うための事業を行っています。
ピースウィンズは、企業版ふるさと納税を通じた地方自治体や企業との連携に力を入れています。寄付金は寄付先の自治体だけでなく各地での活動資金となるため、企業版ふるさと納税制度のメリットを享受しながら、特定の地域に限らない幅広い支援をしたいとお考えの方におすすめです。ここでは、企業版ふるさと納税を通じて支援できるピースウィンズの事業を紹介します。
日本の犬の殺処分ゼロを目指す「ピースワンコ・ジャパン」プロジェクト(広島県神石高原町)

ピースワンコ・ジャパンは、ピースウィンズが運営する保護犬事業です。広島県での殺処分ゼロを2016年から達成し、現在は全国の殺処分ゼロに向けて活動を拡大しています。
国内外の被災地に迅速に駆けつける災害緊急支援プロジェクト「空飛ぶ捜索医療団”ARROWS”」(広島県神石高原町)

空飛ぶ捜索医療団は、ピースウィンズが運営する災害支援事業です。災害支援チームに所属する医師や看護師が平時は町内の診療所等で地域医療に貢献し、災害・紛争など有事の際には神石高原町から国内外の現場にいち早く駆け付けます。特定の自治体への納税でありながら、全国の大規模災害への備えに貢献できる納税先と言えます。
すべての子どもたちに成長の機会を 「ピースワラベ」プロジェクト(島根県隠岐郡海士町)

ピースワラベは、ピースウィンズが運営する子ども支援事業です。児童養護施設や、海士町などの離島で暮らす子どもたちの体験機会が乏しいことに着目し、海外でのスタディツアーなど非日常の経験を通じてソーシャルセクターのリーダーを創出することを目指しています。
まとめ
企業版ふるさと納税の効果を最大化するためには、自社の寄付方針と一致していたり、戦略や事業とのシナジーが期待できたりする寄付先を選ぶことが大切です。
また、付随して得られる恩恵が多く、事業の質が担保されたプロジェクトであれば、CSRおよびESGの観点で考えても、ステークホルダーからの高い評価を得られやすいでしょう。
企業版ふるさと納税の制度概要やメリットは、以下の記事でも詳しく解説しています。
➤企業版ふるさと納税とは?税制優遇の仕組みを完全解説!
➤企業版ふるさと納税のメリット・デメリットを徹底比較!向いている企業とは?
企業版ふるさと納税の仕組みは、ピースウィンズ・ジャパンへの寄付でも活用可能です。ピースウィンズ・ジャパンの事業に関心があり、少ない負担で寄付をしてみたいという方は、以下のページよりぜひともお問い合わせください。













