【 連携事例紹介 】// Contents
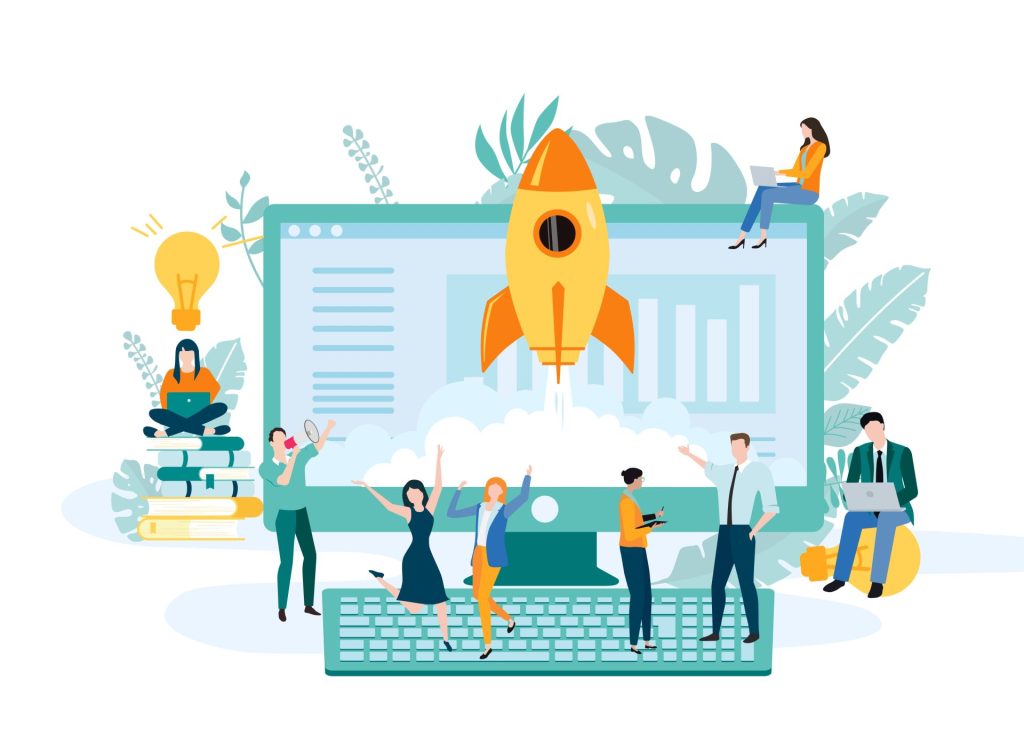
近年、国内外の環境や社会をめぐり、さまざまな課題が山積みになっています。
こうしたなかで、企業が社会的な存在であることを示し、自社のビジネス環境をより良いものにしていくうえで、社会貢献活動の重要性が高まってきました。
しかし社会貢献活動には、注意点もあります。それは、多様な方法で始められる一方で、思いつきで選んだ取り組みを場当たり的に実施するだけでは、効果を最大化しにくい点です。また、社内メンバーの共感や積極的な参加が得られなければ、中長期的な成果につなげることは難しいでしょう。
今回は、社会貢献活動の効果を最大化するために「社内メンバー」を巻き込み、成功につなげていくための処方箋を紹介していきます。具体的には、ゴールの明確化や戦略設計、社内浸透の重要性などについて解説します。
これから社会貢献活動に挑戦する企業担当者の方や、現在行っている活動をさらに良いものにしていきたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
ポイント①:社会貢献活動のゴールと目的を明確にする

あらゆる意味で効果的な社会貢献活動とは、自社の経営戦略やビジョンなどに合ったものでなければなりません。それはつまり、他社の真似をしただけの取り組みでは、自社にとって最大の効果は得られにくくなることを意味します。
社会貢献活動の効果を高めるためには、まず自社ならではの社会課題を設定したうえで、ゴールや目的の明確化につなげていくことが大切です。この章では、具体的な方法とポイントを解説します。
自社が取り組むべき社会課題の見つけ方
本質的な意味で自社の視点や事業活動に合う社会課題を見つけるためには、まずはSDGsゴール、国や自治体・業界団体などのレポート・白書などに目を通し、社会課題の全体像を多面的かつ俯瞰的に掴んでいくことが大切です。
この作業のなかでは、実践的フレームワーク「SWOT分析」を活用するのも一つです。

SWOT分析とは、自分たちのビジネス環境(内部/外部)について、「プラス要因」と「マイナス要因」の両面から分析するフレームワークです。
たとえば、自社の内部にあるブランド・組織力・商品サービス品質などを、「強み」と「弱み」に分類します。一方で外部要因(異常気象・災害・市場のトレンド・競合の動向・技術革新・コストの高騰・過疎化 など)については、自社に影響を与える特徴から「追い風になるもの」「向かい風になるもの」のいずれかに分類していく形です。
たとえば、「幅広い年齢層の人が使える衛生用品」を取り扱う日用品メーカーA社の例を考えてみましょう。A社は製品力には自信があるものの、認知度やブランド力に乏しく売り上げが伸び悩んでいることが課題です。
一方で、国内では「自然災害の増加」という現象が起こっています。災害と言えば、企業にとってコスト増加やサプライチェーンの寸断などを引き起こす重大なリスク要因です。しかし、上記の強みと弱みを踏まえれば、A社にとっては自社製品が力を発揮する「機会」にもなり得ます。つまり、SWOT分析の枠組みで事業環境をとらえることで、「災害被災地に製品を寄付することは、自社の弱みであるブランド力と認知度アップの追い風になる可能性が高い」といった方向性が見えてくるでしょう。
また、社内メンバーの幅広い視点から社会課題の洗い出しを行いたい場合は、管理職向けや若手社員向けなどの階層別研修のなかでワークショップを実施するのも一つです。
経営方針との一貫性チェック
社会貢献活動で取り組む対象課題は、自社の経営方針に合うものを選ぶ必要があります。そこで意識したいのが、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)です。各概念の意味は企業ごとに異なる部分もありますが、一般的には以下の意味で使われることが多いでしょう。
【ミッション】
組織の内外に向けた存在目的。「自分たちは何のために存在するのか?」や「どこに向かって進むのか?」など。経営理念・企業理念に近いもの。
【ビジョン】
ミッションの達成で実現する世界をあらわしたもの。
【バリュー】
ミッション・ビジョンを実現するために大切にしたい価値観、行動、考え方など。行動指針や行動規範に近いもの。「クレド」とも呼ばれる。

たとえば、ミッションが「衣服の提供を通して、世界の人々に安心や幸せを届ける」だった場合、解決すべき社会課題や社会貢献活動の対象は「衣服に関するもの」になってくるでしょう。
具体的には、「災害避難所への衣類の寄付」や「衣類のリユース・リサイクルを通じた募金活動」なども選択肢に入ってくるかもしれません。
自社にとっての目的・目標を設定
企業の社会貢献活動は、寄付・寄贈・ボランティアなどを「実施さえすれば良い」というわけではありません。
社会課題の解決はもちろん重要なことですが、その活動に取り組む社員のモチベーションを高めてより良い成果を出し、会社の成長につなげてくためには、「自社にとっての目的・目標」を設定する必要があります。
具体的には、「売上アップ」「ブランド力強化」「社員エンゲージメント向上」などが設定されるでしょう。たとえば、先述のSWOT分析の結果から「◯◯地震の被災地支援を通して、自社の弱みである関西圏での認知度アップを図っていく」といった目的も設定できるかもしれません。
目的・目標を活動の成功に役立てるためには、なるべく具体的で計測できるものを設定することが理想です。
また、目的・目標は、あまりに高すぎると非現実的なものとなり、社員を中心とするステークホルダーからの共感を得られにくくなる側面もあります。この問題を防ぐためには、目標設定のフレームワーク「SMART」などを参考にしながら、現実的で達成可能な目的・目標を考えることも大切でしょう。

ポイント②社会貢献活動の戦略を設計する
社会貢献活動の成果を最大化するためには、適切な戦略を立てることも大切です。戦略とは、最終的な目標達成に向けてとるべきアクションプランの総称になります。戦略設計のポイントを見ていきましょう。
社会貢献の複数の選択肢
企業が行える社会貢献活動には、本業の自社製品を絡めた「物的支援」のほかに、ボランティアや教育サポートなどの「人的支援」、寄付や奨学金プログラムなどの「資金的な支援」といったさまざまな種類があります。
活動の効果を高めるためには、「どの種類の支援をどういう方法で取り組んでいくか?」について、先ほど決めた自社の寄付目的や関連性が高い社会課題を踏まえて検討していくことが大切です。
また、リソースや人脈などの問題から自社だけでの活動が難しい場合、社外ステークホルダー(NPO・自治体・取引先など)との協業を視野に入れるのも一つでしょう。
たとえば、自社の強みを活かした被災地支援を行いたいものの、現状では現地とのつながりがなく物理的な距離も非常に離れている場合、そのエリアで事業展開する取引先とコラボレーションをすることで「自社の製品を被災地に届ける」といった取り組みも行いやすくなるかもしれません。

協業による社会貢献活動をプレスリリースなどで発信すれば、コラボした取引先にとっても社会的価値を高める良いきっかけになるはずです。社会貢献活動の戦略立案では、ステークホルダーを良い意味で「巻き込むこと」も成功のカギになっていくでしょう。
迷わないためのKPI設計
社会貢献活動を行ううえでは、プロジェクトが迷走や頓挫しないための仕組みも必要です。そこで活用したいのが、数値目標の達成度を可視化するための指標「KPI(Key Performance Indicator=重要業績指標)」になります。
たとえば、飲食業や食品メーカーが行う被災地支援で「フードトラック」や「炊き出し」などをする場合、「利用者数」やそこで配布した「無料クーポンの使用率」といった数字もゴール達成への進捗を見る目安になってきます。
また、最近では新たなKPIの方向性として「インパクト指標」が注目されています。
インパクト指標とは、「事業や活動の結果として生じた社会的・環境的な変化や効果を示す指標」です。具体的には、交通渋滞・災害被害・医療アクセス・健康寿命といった分野に関するものであり、従来KPIと比べて社会課題との関係が深い指標になります。
たとえば、人口減少が著しい過疎地域や交通渋滞問題が著しいエリアにおいて、自社製品であるドローンを使った買い物代行の支援などを行うと、「転出者の減少」や「宅配業者の負担減」といった社会的インパクトに関係するKPIを高めていきやすいかもしれません。
先述の目的・目標、ここで設定したKPIは、社会貢献活動に携わるチーム・社内メンバー全員で達成を目指していくものです。社内で合意を得ることも大切でしょう。
ポイント③小さな成功を積み重ねる
社会貢献活動は、どちらかといえば中長期的な視点を持ってコツコツ進めていくものです。その活動のなかで大切になるのは、「小さな成功体験」を積み重ねるという考え方になります。具体的なポイントを見ていきましょう。
小さく始めて大きく育てる――スモールスタートのすすめ
会社として初めてチャレンジする社会貢献活動は、コストやリスクを抑えるうえでも、小規模・限定的に始めることが大切です。この考え方をスモールスタートと呼びます。
スモールスタートのメリットは、最初のうちは小規模で、人やお金などのリソースもあまり投入していないため、万が一うまくいかないときにも軌道修正しやすい点です。また、スモールスタートには、小さな成功体験から「我々にもできる!」などの自信(自己効力感)につなげていきやすい利点もあります。

たとえば、最初から「物品寄付を行い関西全域に認知してもらう」といった大きなゴールを設定してしまうと、目に見える成果が出るまでに「この方法で本当に良いのだろうか?」などの不安が生じたりするかもしれません。
一方で「◯◯県◯◯市の避難所でフードトラック支援を行う。そこでまずは、自社製品を食べていただければ……。」といった小さなスタートであれば、「皆さんが喜んでくれた」「自治体関係者とのつながりもできた」などの小さな手応えから、「我々にも社会貢献活動ができる!そこから認知度も高められそうだ!」などの自信が生まれていくでしょう。
近年は、原材料費・人件費などの高騰やコロナ禍といった予測不能な変化が起こりやすいVUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代です。こうしたなかで企業がさまざまな課題を乗り越えながら社会貢献活動を続けていくためには、スモールスタートだからこそ早く得られる「自信」が大きなカギになります。
次につながる進め方
社会貢献活動の成果を最大化するためには、取り組みをブラッシュアップするための仕掛けも必要です。そのためには、まずターゲットやテーマを絞って取り組みを企画し、今回の目標と成果の「測り方」を最初から決めておく必要があります。
たとえば、自社周辺のビーチクリーン活動(いわゆるゴミ拾い)を定期的に行う場合、作業前に「参加人数」をカウントし、作業後に「回収したゴミの量」を測定して管理する仕組みが必要でしょう。また、参加者の感想を積極的に収集することも、ステークホルダーに寄り添ううえで大切です。
取り組みの実施後は、必ず振り返りを行います。
たとえば、「朝、駐車場周辺が大混雑していた」や「軍手を忘れる人が多かった」「ゴミ袋は1グループ1枚ではなく、1人1枚にしたほうが良い」といった気づきは、取り組みの改善に活かされるでしょう。
今回の内容を踏まえて次の方針が決まったら、社内外へのアナウンスを早めに行います。

社会貢献活動の実施~効果測定~振り返り~改善策の立案の4ステップを繰り返すと、取り組みが徐々にブラッシュアップされていくでしょう。
ポイント④社内浸透を成功させる
社会貢献活動を本当の意味で成功させるためには、社会課題を解決していく取り組みについて各社員からの理解・共感を得ることが大切です。
また、情熱を持って活動に取り組んでもらうためには、それぞれの意識を「他人事」から「自分事」に変えていくことも大切になります。それは「当事者意識を持ってもらう」や「自分ごと化」などと呼ばれるものです。
社員の自分ごと化を進めるためには、社会貢献活動に力をいれる会社の「あり方」を社内に浸透させる取り組みが必要です。ここでは、あり方を社内浸透させるポイントを紹介しましょう。
社会貢献活動を重視する会社の方針を共有する
全社的に取り組む社会貢献活動は、経営陣が主導してこそ成功するものです。
そのため、これから新たな社会貢献活動に挑戦する場合は、目的や実施計画、その取り組みが経営戦略と結びついた優先事項であることなどを社長メッセージとして経営陣から全社員に発信してもらう必要があります。
そこで経営陣が社会貢献活動の本質的な意味を理解していなかったり、社長の当事者意識を醸成できないまま部門主導で活動を始めたりすると、企業文化としての社会貢献活動が浸透しづらくなります。
その場合、現場の管理職や担当者から「なぜそんなことをする必要があるのか?」などの疑問や反発が生じやすくなるかもしれません。
こうした問題を防ぐためには、まず経営陣に対して社会貢献活動を行う企業のあり方や実施しないリスク、期待できる経営面での効果などを共有し、当事者意識を持って主導してもらえる状態をつくる必要があるでしょう。
それはつまり、経営陣のなかに当事者意識が育まれてはじめて、社員を動かせるだけの社長メッセージが発信できることを意味します。
社会貢献と自分たちを結びつけるストーリーを発信

社長メッセージを発信したら、次は社会貢献活動を社員にとっての「自分事」にする取り組みを進めていきます。そこで活用したいのが、「共感ストーリー」です。
たとえば、大地震の被災地支援を行う場合、そのエリアが「自社製品に欠かせない原材料の一大産地であること(生産者さんが大変な想いをされていること)」や「いつも工場見学に来てくれる小学生の地元であること」などを物語化して発信することで、社会貢献活動と社員の距離がグッと縮まりやすくなります。
それは「他人事」から「自分事」になる瞬間でもあるでしょう。
こうした共感ストーリーによって当事者意識などを向上させることを「ストーリーテリング」と呼びます。物語は、社内広報や朝礼、階層別研修などで発信してもよいでしょう。
また、多くの社員から共感を得るうえでは、独自の動画を製作するのも一つです。たとえば、実際に現地ボランティアに行ったメンバーの感想や、参加してみようと思ったきっかけなどを動画にまとめると、活動参加に躊躇する社員の背中を押しやすくなるかもしれません。
この動画は、社会貢献活動に興味を持つ新卒学生向けにも発信することで、採用活動にも活用できるでしょう。
参加しやすく、やりがいを生む仕掛けづくり
社会貢献活動を全社的に盛り上げていくためには、一人でも多くの社員が参加しやすく、「もっと活動したい!」などと感じてもらえる仕掛けをつくることも大切です。
たとえば、社員から意見や取り組み案を募る、社員投票で方針を決める、活動メンバーを公募する…といった意欲次第で積極的に関われる仕組みをたくさんつくると有効になります。
また、社員参加型の取り組みを行う場合、気軽に参加できる小さな活動を参加の入口として用意し、最初の一歩を踏み出せるよう促すことも大切です。
ただし、社員参加の仕組みをつくるうえで、一つ注意点があります。
それは、各社員の積極的な活動参加は、現場の管理職や他メンバーの理解と業務に支障がでない仕組みがあってこそ実現できるということです。
それはつまり、管理職や同僚などが「現場は自分たちでなんとかするから、ぜひ行っておいでよ!」と送り出せるような風土と体制の整備も、社会貢献活動を全社的なものにするうえで大事な要素になります。
現場の意識を変革するうえでは、社会貢献活動への参加と人事評価を紐づけることも一つです。人事評価の項目に「被災地ボランティアへの参加」などを盛り込むと、会社としての本気度も伝わりやすくなるでしょう。
「成果」や「感謝」を見える化する

社会貢献活動の成果は、積極的に発信しましょう。
たとえば、KPIの進捗はもちろんのこと、「今回のゴミ拾いイベントには300人が参加した」や「自分たちの差し入れ(物品寄付)は、寒い被災地で多くの人に喜ばれた」などの成果レポートを公開すると、社会貢献活動の効果や意義が伝わりやすくなります。
また、社外評価などをメンバー共有する際に、「営業活動のセールストークでぜひご活用ください」とひとこと添えると、社員と社会貢献活動の距離をさらに縮めやすくなるかもしれません。
双方向の改善サイクルを回す
社会貢献活動をより良いものにしていくうえでは、アンケートによる「社内の声」と、一緒に活動を行う外部団体や自治体などからの「フィードバック(社外の声)」を収集し、次の取り組みに活かす必要があります。
社内外の声のなかには、ネガティブなものももちろんあるはずです。
たとえば、「被災地ボランティアでAくんが不在の間に、ほかのメンバーでは対応できないトラブルが起きてしまった」などの声があがれば、人事部門などと協力しながら通常業務を行う現場の体制強化などを進める必要があります。
社会貢献活動を全社的に浸透させるためには、このようにさまざまな部署との調整や交渉も必要となってきます。しかし、取り組み実施後に集めた社内外の声と丁寧に向き合い続けると、多くの人が気持ちよく活動参加できる風土が少しずつ醸成されていきます。
社内報などによる情報発信では、社内外から集めた声とともに、改善したポイントなども共有することも必要です。たとえば、「被災地ボランティアは移動時間も長く大変だという声をいただいたので、2025年5月から独自のボランティア休暇制度を導入しました。」などとアナウンスすると、参加者の増加につなげやすくなるでしょう。
なお、ボランティア休暇制度は、厚生労働省でも導入を推進している制度です。以下の資料では、就業規則の記載例なども紹介しています。ぜひチェックしてみてください。
まとめ
社会貢献活動の効果を最大化するためには、ゴールや目的・目標を明確化したうえで、社内メンバーを巻き込む仕組みをつくることが重要です。また、社内メンバーからの共感を得るうえでは「ストーリーテリング」、小さな成功から自信を積み上げていくためには「スモールスタート」といった手法や考え方も大切になってくるでしょう。自社だけでの活動が難しい場合、社外ステークホルダーとの協業も選択肢にあがります。
ピースウィンズ・ジャパンは1996年の設立以来、国際人道支援、災害緊急支援をはじめとするさまざまな領域で、多くの支援実績を積み重ねてきた認定NPO法人です。当団体には、社会貢献を志す企業様との豊富な連携実績があります。過去の事例集やお問い合わせはこちらをご覧ください。













